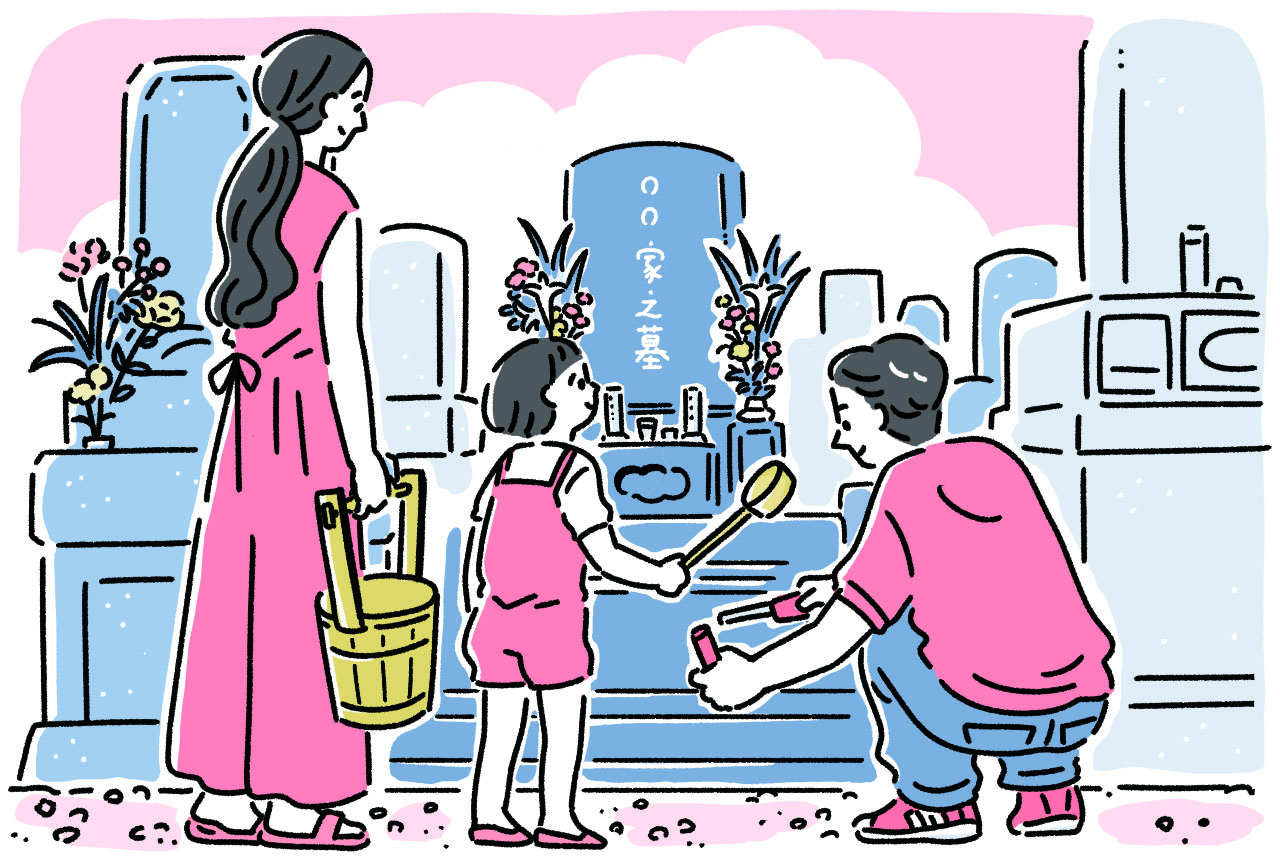そもそも「法要」の意味とは?
法要とは、故人を追悼するために行われる儀式です。主な法要には、故人が亡くなってから百日目まで営む忌日法要(きじつほうよう)と、決まった年の命日に行う年忌法要(ねんきほうよう)があります。
仏教では主に、忌が明ける四十九日までを「中陰(ちゅういん)」と言い、7日ごとに計7回の法要が営まれます。これは、あの世で7日ごとに7回、生前の善行や罪に対して審判が行われるという仏教の考えから、それぞれの審判の日に供養を行い、故人が浄土へ行き、成仏できるように願う意味があります。
法要は自宅や寺院で行われることが多く、僧侶の読経の後、お斎の席を設けるのが一般的です。
法要が重要とされる忌日法要
亡くなってから百日目までの法要を「忌日法要」と言います。
忌日法要一覧
・初七日(しょなのか):死後7日後
・二七日(ふたなのか):死後14日後
・三七日(みなのか):死後21日後
・四七日(よなのか):死後28日後
・五七日(いつなのか)or三十五日(さんじゅうごにち):死後35日後
・六七日(むなのか):死後42日後
・七七日(なななのか)or四十九日(しじゅうくにち):死後49日後
・百か日(ひゃっかにち):死後100日後
※すべて死亡日を含みます。
以前はすべてにおいて、親族でお寺に行くか僧侶を呼んで読経をしていましたが、現在では、初七日と四十九日法要の2回に省略するのが一般的です。中でも初七日、三十五日の法要は遠方の参列者への配慮から、葬儀の日に合わせて行うことが多くなっています。
四十九日は「満中陰(まんちゅういん)」といい、一般的にこの日をもって忌明けとされるほか、四十九日は故人の死後の行方が決まる日とされ、初七日と同様の盛大な儀式を行います。また、この日に納骨式を合わせて行うことも多いです。ただし、宗派や地域によっては、日数の数え方や忌明けの時期が異なる場合もあります。
一周忌以降は徐々に身内だけでの法要に
死亡した同月同日の命日を「祥月命日(しょうげつめいにち)」といい、祥月命日に行う法要を年忌法要といいます。亡くなった翌年に行うのが一周忌、その1年後が三周忌です。その後は七回忌、十三回忌…と続きます。
命日の数え方ですが、法要を営む時は、故人の祥月命日をもとに考えます。故人が亡くなってから、まる1年目に当たる祥月命日が一周忌、3回目以降は亡くなった年を含めた数え方(数え年)になります。例えば、三回忌は亡くなってから満2年目、七回忌は亡くなってから満6年目と数えていきます。
年忌法要一覧
・一周忌:死後1年目(死亡年を含まない)
・三回忌:死後3年目(死亡年を含む)
・七回忌:死後7年目(死亡年を含む)
・十三回忌:死後13年目(死亡年を含む)
・十七回忌:死後17年目(死亡年を含む)
・二十三回忌:死後23年目(死亡年を含む)
・二十七回忌:死後27年目(死亡年を含む)
・三十三回忌:死後33年目(死亡年を含む)
・五十回忌:死後50年目(死亡年を含む)
・百回忌:死後100年目(死亡年を含む)
年忌法要は本来、祥月命日に行うのが習わしですが、参列者の都合を考え、土・日曜に行われることが多いようです。その場合、必ず命日よりも前に法要を行います。一般的には、三十三回忌が最後の法要で、「弔い上げ」と呼ばれています。
穢れた見を慎む「忌中」と、弔意を表す「喪中」
日本では古くから死を「穢れ(けがれ)」とみなす風潮があり、そこかれ生まれたのが「忌」「喪」の考え方です。忌中は死に接して穢れた身を慎み、喪中は弔意を表すという意味があります。一般的に四十九日までを「忌中」、1年間を「喪中」としています。
喪中は慶事への出席や年賀状、神社への参拝などを控えます。年賀状でやりとりを行っている方は、亡くなった年の12月までに年賀欠礼のハガキを出すのが一般的です。
近年は簡略化や省略されることも多い法要ですが、亡くなった方を弔うための大切な儀式です。形式にとらわれずとも、亡くなった方に心を寄せる日は大切にしたいものですよね。